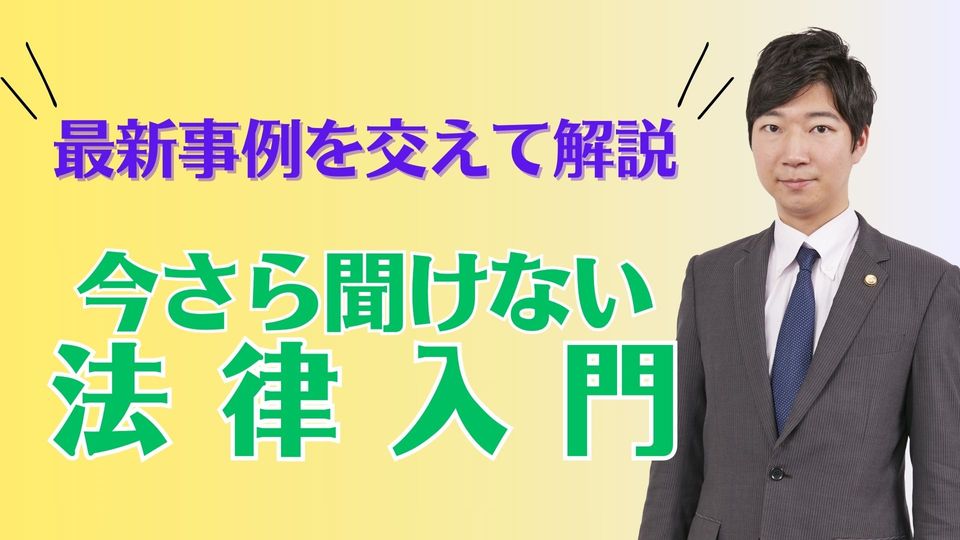健康食品や化粧品の通販における薬機法、特定商取引法、景品表示法の順守がより厳しく求められている。違反に該当すれば、業務停止や罰則の対象となるだけでなく、社会的な信頼を失うことになる。本連載では、それぞれの法律に沿った基礎的な表示のポイントを、最新のケーススタディーを交えて解説する。薬機法・特商法・景表法などに詳しい、名川・岡村法律事務所の中山明智弁護士は、近年の広告表現について、「含有成分の効果として、医薬品的な効能効果を説明しているケースがあるが、特定商品の広告として薬機法違反になる可能性がある」と話している。
――薬機法ではどのような規定がされているのか?まず、薬機法68条を押さえておかなければいけない。
医薬品として厚労省の承認を得る前の商品は全て、名称・製造方法・効能において〝広告をしてはいけない〟ということが68条には書かれている。
一見、化粧品には関係がないように捉えられるかもしれないが、「医薬品」とは何か。
薬機法第二条によれば、医薬品とは「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」、「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」と定義されている。
要するに、化粧品として販売しているつもりであっても、〝薬っぽい広告〟を出していると、法律的には医薬品の定義に該当している場合があり、その場合に厚労省の承認を得ないまま医薬品のような効果・効能に関する広告を書いてしまうと、薬機法68条違反となる。
――違反に該当しないためにはどんな書き方をすればいいのか?平成29年に改訂された「医薬品等適正広告基準」や「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について」を見ると、具体的な規制の内容が分かる。
例えば、化粧品であれば、広告に使用できる効能効果に関する表現は56個に絞られている。化粧品として販売したいのであれば56項目に準じて表示する必要がある。
――違反に該当する例・しない例を具体的に知りたい。分かりやすい例として、アトピーの治療など病気が治せると認識される書き方は基本的にはNGだ。血行促進、肌質改善など体の内部にまでアプローチすると認識される表現も違反になる。
一方、「肌に潤いを与える」「乾燥を防ぐ」など〝保護する〟意味合いの表現や、「肌にハリを与える」「ツヤを与える」など、表面的な部分にアプローチする表現は違反に該当しない。
56項目以外の表現を使用したい場合は、厚労省の承認を得て医薬部外品として販売するなどの手段もある。
――そもそも何が「広告」に該当するのか?広告の3要件が全てそろうと広告とみなされる。広告の3要件とは「顧客を誘引する意図があること」「特定の商品名が明らかになっていること」「一般人が認知できる状態にあること」――の3つだ。
ウェブ広告やテレビCMはもちろん、商品に同梱するチラシなどももちろん該当する。
――実際に68条に違反するとどのような罰則があるのか?68条違反による罰則は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となっている。
薬機法は特商法や景表法と異なり、「何人(なんぴと)規制」と呼ばれ、事業者でなくても、誰しもが罰される法律だということにも注意したい。SNSなどでPRを行うインフルエンサーにも適用される。
――薬機法の課徴金について知りたい。2021年に薬機法の課徴金制度が施行された。課徴金制度とは、裁判をせずに行政が罰金できる仕組みだ。
もともと薬機法は刑事罰しかなく、捜査・逮捕・起訴・刑事裁判という過程を踏まなければ罰することができなかった。しかし、全てを摘発するのは事実上不可能ということで、課徴金制度が導入された。
現在、まだ施行された事例はない。
ただ、薬機法の課徴金は売り上げの4.5%。仮に1億円の売り上げがある化粧品の広告で罰せられば、450万円収めなければならないので要注意だ。
――他に事業者が知っておくべきことはあるか?最近では、「商品説明ではなく成分の説明であれば、薬機法は適用されない」と勘違いしている事業者が多く、商品の広告ページで成分の効果効能を表示してしまっているケースもある。
仮に成分Aの説明であっても、その会社が成分Aを含む商品を販売していれば、「特定の商品名が明らかになっていること」とみなされるケースもあるだろう。
ウェブ上で成分Aを説明するページから1クリック、2クリックで成分Aを含む商品の購入ページに飛べる場合には注意が必要だ。