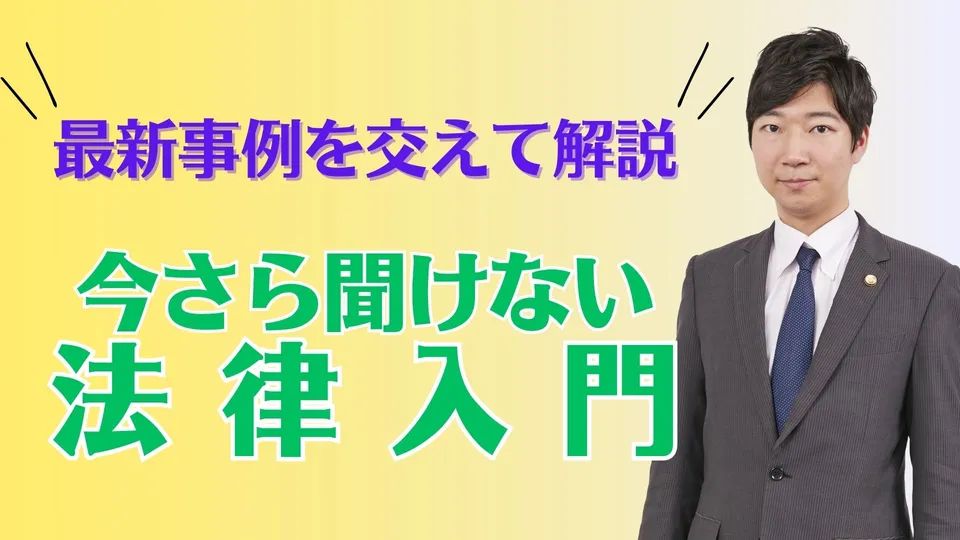健康食品や化粧品の通販における薬機法、特定商取引法、景品表示法の順守がより厳しく求められている。違反に該当すれば、業務停止や罰則の対象となるだけでなく、社会的な信頼を失うことになる。本連載では、それぞれの法律に沿った基礎的な表示のポイントを、最新のケーススタディーを交えて解説する。第2回は薬機法や景品表示法に詳しい中山明智弁護士に、近年の健康食品の広告表示の問題点と事業者が注意するべき点について聞いた。
――薬機法に抵触するウェブ広告は昨今、どんなものがあるか?以前からよく見る広告表現ではあるが、「腸活」や「痩身」をうたうサプリメントの広告には、薬機法に触れるような表現のものも現状、多く見受けられる。
前提として、薬機法では、疾病の治療・予防を期待させる表現や、身体機能の増強・増進を暗示させる表現はNGとされている。
「痩身」を訴求するサプリメントの「飲むだけで痩せる」という表現は、痩せやすい身体に変化させるという意味にとられるため気を付けたい。
さらに「食欲の抑制」も、医薬品的な効果効能に当たってしまうのでNGだ。
また、コロナ禍では、「免疫」を表示して薬機法に抵触する表現をしているサプリの広告が多数見られた。
――どのように表示すれば違反にならないのか?例えば痩身に訴求するサプリメントの場合、「通常の食品に置き換えられる」という表現は可能だ。「栄養の補給であればOK」という1つのルールがあるからだ。「いつもの食事の代わりに、おなかがふくれる、十分な栄養が取れる」という意味合いの表現であれば、問題ないだろう。
ただ、前述のとおり「置き換え」の表現であっても「食欲を抑制する」という表現は、薬機法に抵触する。
あくまで、「おなかをふくらませる」「栄養面で通常の食事の代わりになる」という意味合いの表現にとどめることが必要だ。
――違反する広告表示をした場合、罰則の対象となるのは? 広告主の事業者だけでなく、広告の表示によって利益を得た広告代理店やインフルエンサーが、共犯とみなされる可能性がある。
社長や部長といった責任者が取り調べを受ける可能性もあるし、担当者や代理店が逮捕される可能性もある。
実際に、サプリメントの通販事業者が逮捕された事例もある。違法な広告表現をすることのリスクが高いということは、絶えず意識すべきだ。
――具体的にはどのように注意すればいいか?広告主である事業者や、広告代理店は、商品の訴求力を追求する担当者と法チェックを行う法務担当を社内で分けたり、自社の社員に対して、薬機法や景品表示法、特商法に準じた広告表現についての絶えず教育を行ったり、会社内の意識を欠落させないことが重要だろう。
薬機法に抵触する広告表現をしてしまう会社は、担当者や代表者において順法意識が欠落してしまっているケースが多い。
社長や部長クラスの責任者は、広告担当者や広告代理店、インフルエンサーなどが作成した広告を放置せず、しっかり管理・監視していく必要がある。
何も知らずに、商品の訴求力だけを追求して広告表現を考えてしまうと、薬機法違反に抵触する表現が生まれてしまいかねない。