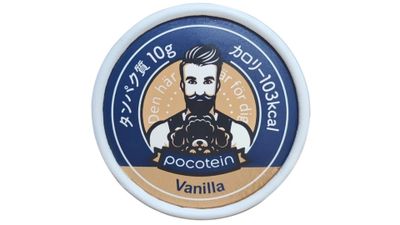コールセンターの声を生かす
同社の商品開発の主軸は、コンシューマ事業本部ダイレクトマーケティング部の商品企画部が担っている。ここでは、マーケティングの視点を起点に、技術開発部と呼ばれる研究開発チームと連携しながら、商品を組み立てていく。
菌の新素材の選定や、エビデンスの収集、機能性表示食品の届け出に適した剤型の検討など、多くのプロセスが存在するという。
特に、機能性表示食品は、届け出から販売まで、1~2年がかかるケースが多いとしている。素材やヘルスクレームによっては3~5年かかるケースもあるそうだ。
同社の健康食品開発は、市場のニーズに応じて柔軟に行っている。すでにラインアップされている自社製品を俯瞰(ふかん)し、未対応のニーズを探るところから、商品開発が始まるという。さらに、研究開発部門から提供される新素材情報を加味して、開発方針を定めるのだという。
市場調査レポートや、自社顧客への定量調査も、商品開発の方向性を見定める上で重要な材料となる。中でも、コールセンターに寄せられる顧客の声は、商品改良の鍵となっているそうだ。
菌の研究と商品化は密接に連携して進められるという。研究開発部門では、乳酸菌をはじめとした菌の機能性に関する情報を収集・分析し、商品企画部門と連携して、どの菌をどのような形で商品に組み込むかを検討しているという。「菌が持つ機能成分をどう加工し、どの剤型で消費者に届けるのか」が、製品の価値を大きく左右すると考えているそうだ。
独自素材でコモデティー化避ける
アサヒグループ食品のコンシューマ事業部ダイレクトマーケティング部の福田美鈴主任によると、「今後の開発テーマとして注目しているのは、『フレイル予防』や『更年期対策』など、女性特有のライフステージに応じた商品群」だと言う。
とりわけ、”予防”段階にアプローチできる商品開発を模索しているそうだ。
福田主任は、「マーケティング目線の商品企画はコモデティー化しがちだ。技術開発部の持つ、新しい菌のエビデンスなどの情報を、消費者の潜在ニーズと組み合わせた商品開発を追求したい」と話している。
アサヒグループ食品では、カルピス由来の乳酸菌という強みを生かし、「菌をどう生かすか」「菌の機能をどう届けるか」を追求し続けることで、差別化を図っているという。