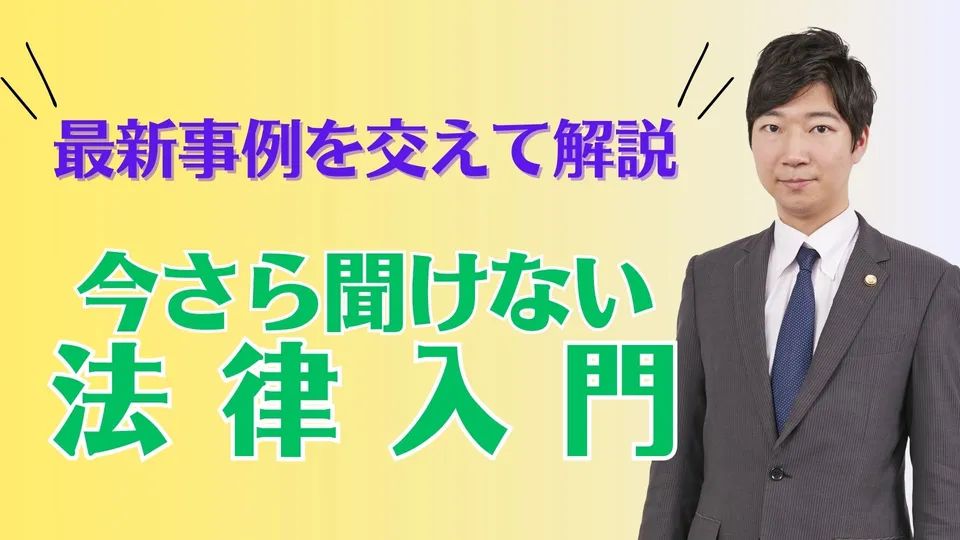健康食品や化粧品の通販における薬機法・特定商取引法・景品表示法の順守がより厳しく求められている。違反に該当すれば、業務停止や罰則の対象となるだけでなく、社会的な信頼を失うことになりかねない。本連載では、それぞれの法律に沿った基礎的な表示のポイントを、最新のケーススタディーを交えて解説する。第3回は景品表示法。薬機法や景品表示法に詳しい中山明智弁護士によると「期間限定のセール価格の表示は、2週間ごとに見直さないと危険」だという。
――なぜ期間限定のセール価格の表示は2週間ごとに見直しが必要なのか?「有利誤認表示」として、景品表示法違反に該当するおそれがあるからだ。
「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも有利であると消費者に誤解させるような表示を指す。
例えば、「通常価格1万円のところを、今だけ5000円」という期間限定の値引きの広告を目にすることは少なくない。
ここでは「通常価格」の定義が肝となる。
「通常価格」とは、直近8週間のうち、半分以上の期間で売られていた価格でなければならない。直近8週間のうち、少なくとも4週間は1万円で販売した実績がないと、1万円を通常価格と告示することはできないのだ。
さらに、通常価格と表示された価格で最後に販売した日から、2週間が経過してしまった場合も、通常価格と表示することはできなくなる。
例えば、最後に1万円で販売した日から2週間以上経過しているのに「通常価格1万円のところ、今だけ5000円」という広告を出していたら違反とされる。
したがって、通常価格と比較して表示する割引価格の表示については、2週間ごとに見直す必要があるだろう。
――発売から8週間経過していない場合は?発売期間が8週間未満の場合、発売からの半分以上の期間で売っている価格を、通常価格とする。
例えば、発売から6週間であれば、3週間以上販売している価格を、通常価格と表示できる。
ただし、通算で2週間以上販売していなければ、通常価格とは認められない。
発売から2週間しか経っていない商品であれば、半分の期間は1週間だが、1週間しか販売していない価格を「通常価格」と表示することはNGだ。
――他に景品表示法について注意すべきことは?主な発覚ルートは3つある。
1つ目は消費者から消費者庁への通報、2つ目が同業他社からの情報提供、3つ目が行政による定期的なパトロールだ。
優良誤認表示については、消費者から「広告の通りの効果が得られなかった」や、同業他社から「この成分内容で、表示されている効果は得られないはず」などの通報がされることがある。
消費者庁には、表示に関する通報が日常的に寄せられており、それをもとに調査が始まるケースも多数ある。
過激な表現や極端な表現をしていると、エビデンスの提出を求められやすい。
薬機法に注意することが、結果として景品表示法の対策にもつながるだろう。
――ステルスマーケティングとその規制についても知りたい。次回はステルスマーケティングについて、事例を交えて解説する。
「優良誤認表示」や「有利誤認表示」と並ぶ、景品表示法違反のパターンの1つに「内閣総理大臣が指定する表示の7パターン」があり、その中の1つに、ステルスマーケティングが含まれる。
ステルスマーケティングとは、広告であるにもかかわらず広告であることを明記しない、SNS投稿や情報発信のことだ。物販や通販事業をするうえで、知らなければならない内容となっている。