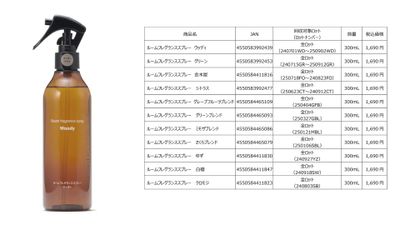ベネッセコーポレーション(本社岡山県、岩瀬大輔社長)では近年、「進研ゼミ」などの通信教育の分野で、生成AIの活用の取り組みを強化している。生成AIの活用について、サービスを開始した2023年ごろは保護者の意見が割れていたが、最近は肯定する保護者が増えているという。共働きが増加し、「子どもの勉強を見る時間が取れない」といった家庭が増えたことも、要因となっているようだ。近年の通信教育の動向と、生成AIを中心とした取り組みについて、小学生事業部本部長の水上宙士氏に話を聞いた。
──近年の通信教育の動向について聞きたい。
「子どもの数」という分母は下がり続けているものの、市場はそこまで変わっていない。小学校や中学校への入学や、初めて成績が出たタイミングなどで、通信教育を始める人が多い。「学校の授業にプラスアルファしたところまで学習したい」という人もいるが、市場的には「学校の授業についていけるようにしたい」という人の方が多い。
──通信教育の販促物に変化はあるか。
販促物に関しても、昔と変わらずDMが根強い。DMは保護者向けのもの以外に、子ども向けのものも発送している。近年では、子ども向けのDMが強い印象だ。
昔と比べ、郵便物を子どもが取りに行くケースが増えているのかもしれない。子どもからすると、自分宛てに荷物が届くということは、あまりないだろう。そんな中、「自分の名前で来ているからとりあえず開けてみよう」となり、見てもらえているのではないか。
好きなクリエーティブが変化
「進研ゼミ」のDMには従来、「進研ゼミによる成功体験」などを描いたマンガを掲載していた。だが最近は、子どもの好きなクリエーティブが変わってきている。以前から「活字を読むと疲れる」という子どもはいたが、今では「マンガを読んでも疲れる」という子どもまでも出てきている。より子どもが興味を持つクリエーティブを作っていくことが重要になっていると考えている。
──学習内容に変化はあるか。
昔は「受験」が前提にあったため、受験で使う5教科を学ぶ人が多かった。だが近年は、定期テストにある9教科を学習する人が増えている。美術や音楽といった実技科目は、教えている塾が少ない。だが、テストはあり、その成績で内申点などが変わってくる。「塾に行くほどではないが、実技科目の対策はしたい」といった人が、当社の通信教育を選択しているのだろう。
AIで自由研究
──生成AIの活用についても聞きたい。
ユーザー向けでは、2023年7月に、「自由研究お助けAI」という生成AIサービスが始まりだ。生成AIを通じて、自由研究のアイデアやテーマを見つけられるようなサービスになっている。
目的外の利用を制限し、1日の質問回数にも上限を設けた。そうすることで、安心して利用してもらえるサービスを目指した。
夏休みの自由研究は、当社のアンケート調査によると、子ども・保護者共に、「最も大変だと思う宿題」のトップだった。保護者が大変だと思う理由は、「テーマが決まらない」「親の手伝いが必須」などで、95%近い保護者が子どもの自由研究に関わっていた。
社内的には、2023年4月から生成AIの活用を進めている。現在だと、録音の要約、メルマガなどの簡単な文章作成、ブレインストーミングの相手として活用している。生産性の向上について、具体的な数字は示せないが、かなり向上しているのではないか。
小学生未満向けだと、「AIしまじろう」のサービスを進めている。ソフトバンクロボティクスと共同開発したもので、生成AIを搭載した幼児向け会話型サービスだ。
しまじろうの声を再現した、「AIしまじろう」と「おしゃべり」や「あそび」ができる。AIしまじろうとの会話やあそびの中で見えた興味や感情は、AIが分析し、保護者にレポートとして提供する仕組みだ。
──今後の通信教育市場をどう見ているか。
子どもの数が減少傾向にある以上、厳しくなっていくことは間違いない。小さくなる市場の中、どれだけ多くの人に、「通信教育」という選択肢を選んでもらえるかが勝負だ。
当社の調査で、「昔と比べ、子どものやる気が下がっている」という結果が出たことがあった。「子どもに勉強させたいけれど、無理やりやらせたくはない」と考える保護者が多いようだ。
自由研究という入り口や、タブレットを活用した楽しめる学習など、「子どもが自分からやりたいと思う勉強」を提供していかないと、今の保護者には納得してもらえない。
今の小学生の親世代は、進路や習い事などを親に薦められ、何となくレールに乗せられて大人になったという人が多いのかもしれない。その反動から、「自分の子どもには、自分で決めて、自由に人生を選んでほしい」と思っている人も多い。
家庭環境や子どもの趣味嗜好(しこう)が変わっていく中、「選んでもらえる通信教育」を目指していきたい。