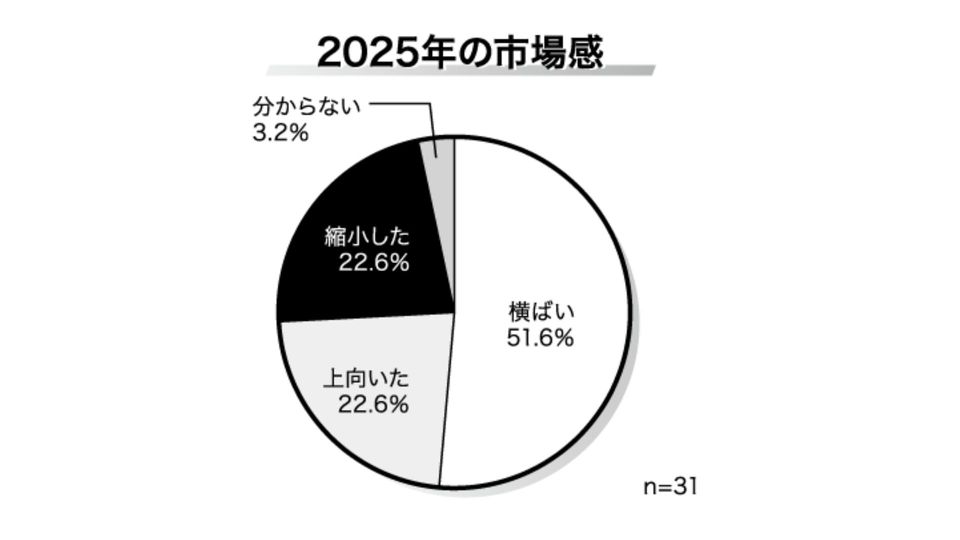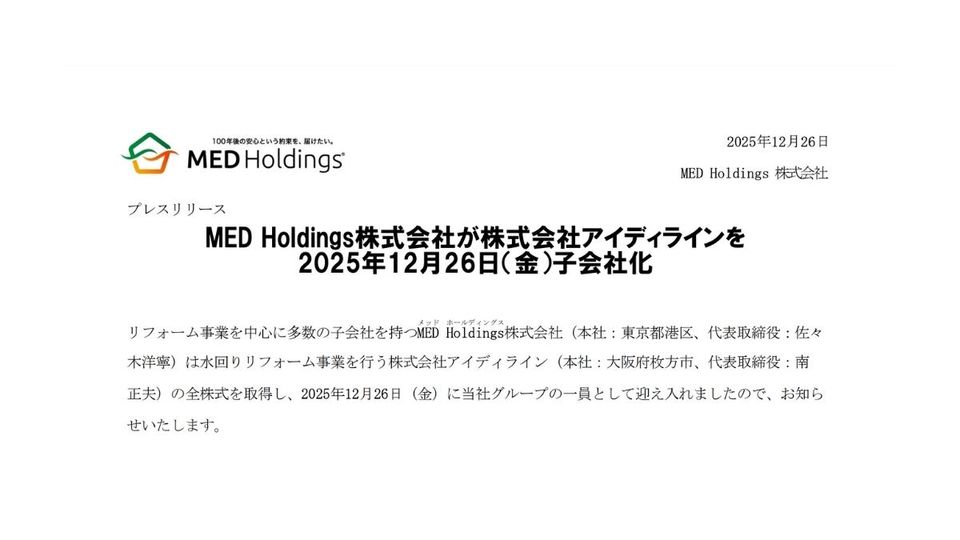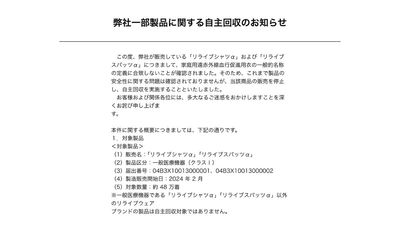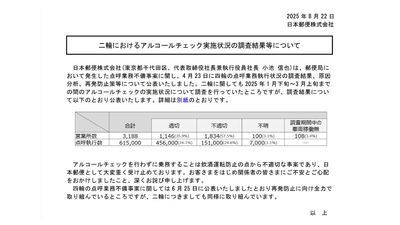高齢化する患者と送迎サービスの拡充
新小岩クリニックは40年以上の歴史を持つ、透析専門クリニックで、腎不全を患う多くの患者が定期的に通院している。透析治療は通常、週に3回、1回あたり3~4時間がかかる。患者にとって時間的・身体的な負担が大きいそうだ。

▲新小岩クリニック
西尾副院長によると、透析導入に至るまでの治療の進歩により、透析導入患者の平均年齢は年々上昇しているという。開院当初は50~60代が中心だったが、現在では70~80代の高齢者が多数を占めているのだという。
患者の高齢化に伴い、足腰が弱くなった通院困難者も増えたとしている。このため、同院では、自宅からクリニックまでの送迎サービスを拡充している。患者の多くがこのサービスを利用しており、高齢化への対応が喫緊の課題となっているそうだ。
疲労軽減とQOL向上を
西尾副院長が電解水透析に興味を持ったのは、東日本大震災のころだったという。電解水透析がかなえる、患者の疲労軽減の効果を知り、「いつか導入したい」という思いを抱き続けていたそうだ。機器更新のタイミングで導入を決定したという。
従来の透析は、血液中の老廃物や、余分な電解質、水分を除去することを主な目的としていた。これに対し、電解水透析は、水を電気分解することで生成される水素を豊富に含んだ透析液を使用する。この透析液が体内の酸化ストレス物質を除去することで、全身の代謝改善を促すのだという。それにより透析後の疲労感の軽減や、粗死亡率の低下、末梢動脈疾患の改善などのエビデンスが得られつつあるそうだ。西尾副院長は「患者さんの疲労感をできるだけ軽減してあげたい」という思いが導入の最大の動機だったと語る。

▲新小岩クリニックが導入した電解水透析多人数用透析用水作製装置
高齢の患者にとって透析の身体的負担は大きい。透析が終わった後に疲れた顔をして家に帰っていく患者を、日々目の当たりにしていたという西尾副院長は、電解水透析がこうした疲労感を軽減することで、患者がより活動的な生活を送れるようになり、QOLの改善につながることを強く期待しているという。
アンケート収集を計画
導入から約2カ月しか経過していない現時点で、すでに患者からは「体が楽になった」という声が聞かれるようになったという。西尾副院長は、今後アンケート調査を実施し、疲労度に関するデータを収集していく予定だ。
栄養指標などの長期的なデータ追跡も行い、学術的な貢献も目指したいと語る。
同院は、今回の電解水透析導入を単なる機器更新として捉えていないという。「1回の透析の質を高めることに強いこだわりを持つクリニックでありたい」という姿勢を示すためのアピールポイントになると捉えているそうだ。
国内の透析患者は現在、増加から減少傾向に転じつつあるという。患者から選ばれるクリニックになるべく、差別化を図る狙いもあるそうだ。
電解水透析の普及に当たっては、「機器の導入にかかる費用」や「設置スペース」が課題になるケースが多いという。
西尾副院長は、「疲れを持ったまま寿命が伸びるよりも、疲れがない状態で寿命が伸びた方がいい」と話している。