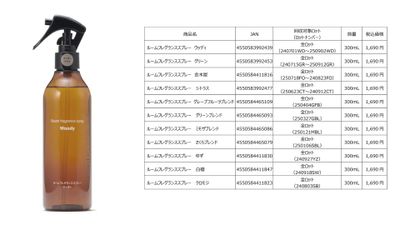ベルシステム24の2025年2月期のCRM事業の売上高は、前期比3.3%減の1431億9600万円だった。コロナなどの国策関連業務の大幅縮小が減収要因となった。今後、同社は外注化ニーズへの対応や生成AIの活用、マーケティング支援などに注力し、2031年2月期までに売上高2500億円、営業利益率10%以上を目指していく。執行役員兼デジタルCX本部部長の加藤寛氏に、前期の振り返りと今期の取り組み、今後の成長戦略などについて聞いた。
──前期は減収だったと思う。業績について振り返ってほしい。
2025年2月期の連結売上高は、前期比3.4%減の1436億700万円、CRM事業の売上高は同3.3%減の1431億9600万円だった。前年と比較すると、連結売上高は約50億円のビハインドで、コロナ禍での特需案件の終了が関係している。一方で営業利益は同0.9%増の116億円となり、既存事業における収益性の改善は着実に進んでいる。
──そのような市況感の中で、デジタル技術や生成AIの活用が加速していくと思う。会社としての取り組み内容について伺いたい。
市況感を見ると、まだ生成AIの導入が企業に思うように進んでいないとみている。多くの企業が生成AIのPoCに着手するものの、本格的な導入には至っていない。それは現存の生成AI活用のアプローチでは、コンタクトセンター業務の本質的な課題を解決できないからだと考えている。
──課題はどこにあると考えているか。
2024年6月に設立した「生成AI Co-Creation Lab.」でさまざまな企業と実証実験や議論を重ねる中で、共通の課題として見えてきたのが、回答の基となるマニュアル、経験や勘などの暗黙知などのナレッジが未整備であることだ。一般的なLLM(大規模言語モデル)は、あくまで汎用的な知識しか持っていない。
そのため、常に最新のナレッジを学習させる必要がある。また、一問一答では解決できない難度の高い問い合わせに関しては、お客さまとの会話から課題を捉えて適切な回答に導くためにガイドする必要がある。一問一答ではないにしろ、ルールベースやシナリオベースで構築に手間をかけて実装しているのが大半だ。
回答を導く手法として、「RAG(検索拡張生成)」が注目されているが、参照元となるデータの情報が古かったり、ベテランの頭の中にしかない暗黙知が文書化されていなかったりと品質に問題があるケースが多い。その結果、RAGを使っても回答精度は60%から80%程度に留まってしまう。
コンタクトセンターではお客さまからの「契約」に関わるような重要な問い合わせも多くあるため、この「精度の壁」が、多くの企業を「PoC」の段階で足踏みさせている最大の原因だと分析している。
──ベルシステム24として、どのように課題を乗り越えようとしているのか。
当社は、コンタクトセンターに蓄積されるお客さまとの対話データに着目し、企業が持つサービス規程などの普遍の情報も取り込みながら、ナレッジを自動生成する仕組み作りを進めている。これが、当社が考える人と生成AIのハイブリッドによる自動化ソリューション「Hybrid Operation Loop(ハイブリッドオペレーションループ)」の礎になっている。
実現には、主に(1)ナレッジの自動生成(通話音声データを生成AIが解析し、常に最新で質の高いナレッジを自動で生成・蓄積する)(2)高精度な検索技術(独自の「ハイブリッドRAG」技術により、ナレッジベースから最適な回答プロセスを導き出し、回答精度95%以上を目指す)(3)高度な自動応答の実現(AIエージェントによる人らしさを追求した回答を行い、人のオペレーターでの対応が必要な案件についてはスムーズに引き継ぐ)─という三つのステップがあると思っている。
対話データを軸に当社が持つ業務知見とAI技術を組み合わせることで、常に最新のナレッジが蓄積され、チャットや電話で問い合わせてきたお客さまに自動で最適な解決策の提案を行うことが実現できる。
──これはコスト削減が主な目的なのか。
もちろん効率化によるコスト削減も大きなメリットだが、当社が見ているのはその先だ。この構想は、コスト削減という「引き算」だけでなく、新たな売り上げを生み出す「足し算」のビジネスを可能にする。コンタクトセンターを「コストセンター」から、新たな価値を生み出す「プロフィットセンター」へと変革させる力を持っている。
──2031年2月期に連結売上収益2500億円、営業利益率10%以上という目標を掲げている。達成に向けて、どのような戦略を描いていくのか。
会社としては(1)外注化ニーズへの対応(2)生成AIの活用(3)マーケティング支援─などに注力していく。この目標を達成するためには、従来の延長線上だけでは難しく、この「Hybrid Operation Loop」は売り上げ拡大に大きく貢献できると思っている。
先ほど申し上げた「足し算」の部分では、インハウス市場の開拓や、新たなBPO領域の拡大、音声データを活用したマーケティング支援といった新事業でトップラインを大きく伸ばしていけるはずだ。
もう一つは「引き算」、つまり収益性の向上だ。AIとの協働により、オペレーター一人当たりの生産性を高め、利益率を改善する。この両方を同時に実現することで、2500億円という目標の達成が見えてくる。