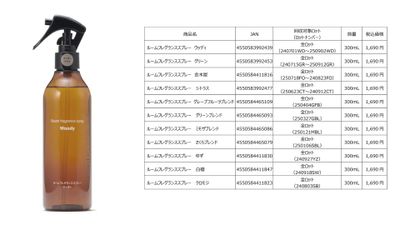全てのチャネルからVOCを収集・分析するサービスは他社でも展開しているが、他社との違いについて、CX事業統括CX事業推進本部共同本部長の岩浅佑一氏は、「ウェブサイトの構築や運営を行っている点が差別化につながっている。ウェブサイト上での顧客の行動という定量的なデータも一元的に把握できる」と話す。
同社のDX戦略の根幹にあるのは、「ユーザーの変化に対応する」という視点だ。近年、若年層を中心にコミュニケーションの主流は電話からチャットを始めとするテキストへと移行している。この変化を捉え、ウェブサイト、チャット、コンタクトセンターなど、あらゆるチャネルから集まるVOCを連携させることに取り組んでいる。
「多くのお客さまは、本心では電話をしたいわけではないと思う。そのインサイトに基づき、自己解決を促すコンテンツをウェブサイトに用意したり、最適なタイミングでチャットに誘導したりして、問題を解決することを目指している」(岩浅共同本部長)と話す。
トランスコスモスは、ウェブインテグレーションにおいて、アジア市場でトップクラスの提供実績を持つ。ただ単にコンタクトセンターを運営するだけでなく、顧客接点の最上流であるウェブサイトそのものを作り、改善し続けている。そのため、同社は「定性的なデータ(顧客の声)」と「定量的なデータ(ウェブ上の行動履歴)」の両方を統合して分析することができるという。
多くのコンタクトセンター企業は、コンタクトセンターの運用が主体であり、分析できるのは「声」のデータに限られる。だが、実際にコンタクトセンターに電話をかけてくる顧客は、ウェブサイトを訪れる顧客全体のごく一部だ。
「当社はウェブサイトを訪れた大多数のお客さまの行動データを詳細に追跡できる。この行動データとコンタクトセンターに寄せられる声のデータを突き合わせることで、『特定のページで離脱したお客さまは結果的に〇〇という内容で電話をかけてくる傾向がある』といった、より深く本質的な顧客理解が可能になる。この統合的なデータに基づいた具体的かつ効果的なアクションプランを提案できることが、他社との違いだと思っている」(同)と話す。
対話可能なAI開発へ
トランスコスモスは2025年3月、チャットボットなどの提供を行うモビルスと合弁で、コンタクトセンター向けのAIエージェントプラットフォームを提供するvottia(ボッティア)を設立した。単なる自動応答システムではなく、親しい友人と会話をするようなAIの開発を目指している。
現在、AIが電話対応するサービスの開発を進めており、リアルタイムで柔軟な会話を実施して、人を介さない解決対応を実現する。AIが質問している途中で、人が返答しても、その内容をAIが即座に理解し、スムーズな応対を続けることができる。
「例えばECサイトであれば、注文の受け付け、配送状況の確認、返品・交換の手続きといった定型的な業務は、このAIエージェントが即座に対応できる。将来的には導入企業さまの基幹システムとAPI連携することで、AIが個々の顧客の購入履歴や会員ステータスを直接参照し、『〇〇さま、いつもありがとうございます。先日ご購入いただいた商品の使い心地はいかがですか』といった、パーソナライズされた高度な会話も可能になる」(同)と説明する。
解決件数4.3倍に向上
トランスコスモスは生成AIチャットボット対応型ハイブリッドチャットサービス「trans-Chat Support」を、日本生活協同組合連合会(日本生協連)が運営するギフト専門オンラインショップ「コープのギフト」に提供したという。
主に(1)生成AIがユーザーの質問文を理解し、適切な回答を提示(2)サポートナレッジ生成による課題解決における生産性向上(3)チャットボットと有人チャットのハイブリッド化による問題解決時間の短縮─などを実現し、1時間当たりの解決件数は電話対応のみに比べて、4.3倍増加した。1件当たりの平均対応時間を約7分短縮することにも成功したという。