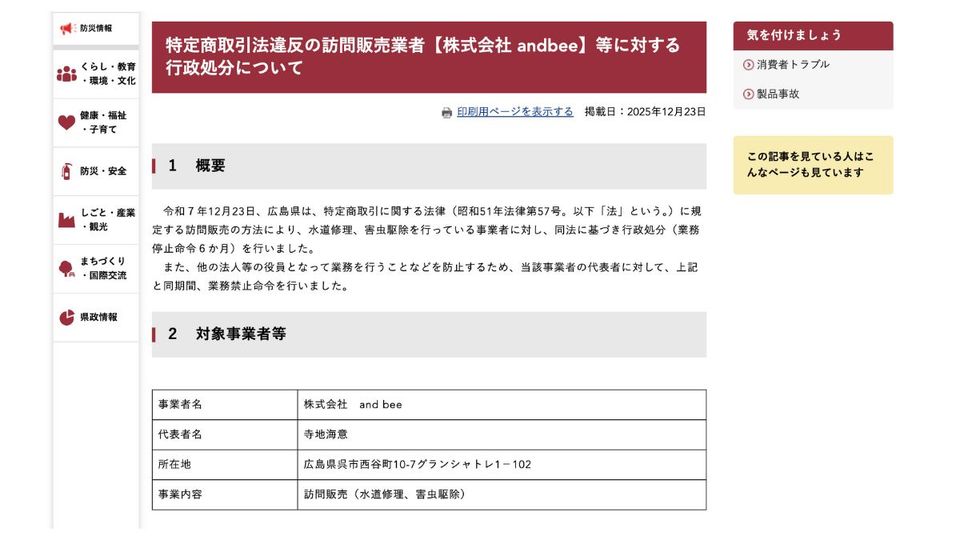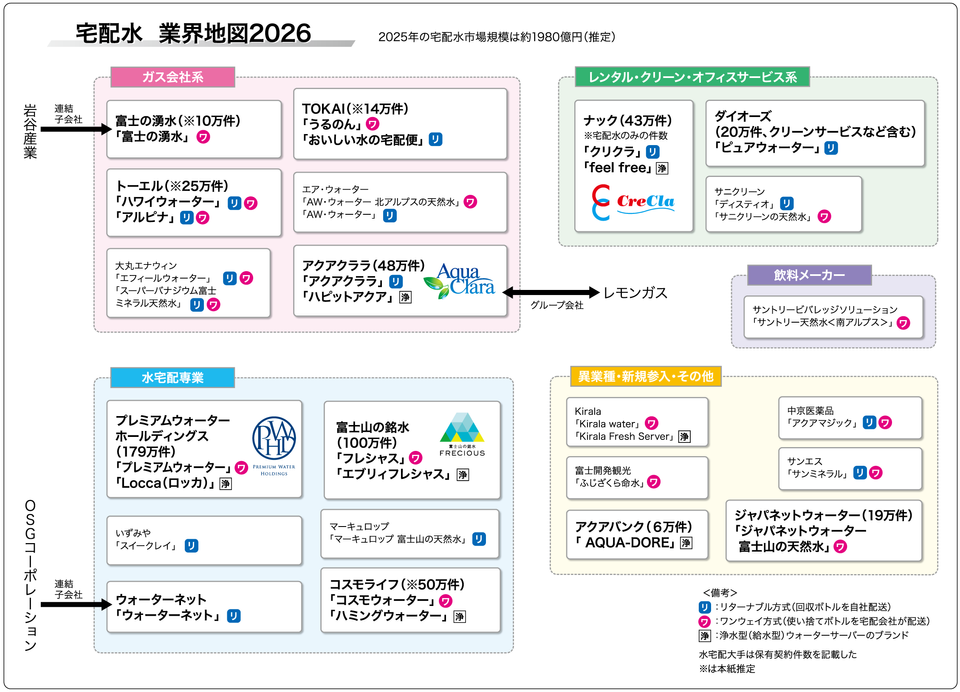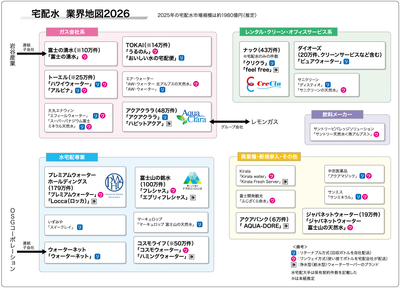コロナ禍でカスハラ防止への機運高まる
──カスタマーハラスメントへの関心が高まった背景は。
カスタマーハラスメントについては、以前から労働問題の一つして認識されていたが、ストレスを多くの人が抱えていた2020年のコロナ禍を境に顕在化した。
社会全体での対応が必要となり、厚生労働省や労働組合などがハラスメント対策などに力を入れ始めた。カスハラの実態調査などを経て、メディアにも注目されるようになり、人材不足の観点からも従業員保護が重視されるようになった。労働問題に端を発したカスハラが経営問題、さらには人権問題に発展してきている。
──カスハラ防止に関する法律や条例の内容については。
厚生労働省は事業者に対して、カスハラ対策を義務化する動きがある。2020年6月の労働施策総合推進法の改正や顧客からの迷惑行為に対する取り組みが明文化されてさまざまな法律や施策が整備されている。
東京都では、2024年10月4日に全国初の「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、2025年4月に施行される。同じく北海道においても4月1日から「北海道カスタマーハラスメント防止条例」が施行される。この条例には、カスハラ行為の禁止と被害者支援を目的とし、罰則は設けていない。
一方で、三重県桑名市では、基礎自治体として初めてのカスハラ防止条例を制定して制裁措置を盛り込んだ。大阪府吹田市では、カスハラ対策として職員向けの啓発活動や相談窓口を設置している。そのほか、札幌市では、2022年にカスタマーハラスメント対策基本方針を策定し、職員教育や研修を進めている。
──業界団体や事業者はどのようなことが必要なのか。
企業としてはすでにカスハラが労災の認定基準になっており、安全配慮義務を含めて早急な対策が必要だ。今後は、企業がカスハラに対する方針を出しているかどうかが、学生などが企業に応募する際の基準になるかもしれない。
ACAPの調べでも、方針を策定しているのは全体の3割で、公表している企業は1割ほどに留まる。業界団体や各社はカスハラ事例を集めた上で方針を策定し、代表者や社長名で公表することが望ましい。また、カスハラ対応窓口の部門や担当者だけでなく全従業員に対しての研修が求められる。2025年から2026年に向けて計画的に行う必要があるだろう。
都では、モデルマニュアルを提示するだけでなく、相談窓口の設置や研修など具体的な支援を考えているようだ。
──カスハラ防止条例に期待することは。
条例やガイドライン、業界団体共通マニュアルの三つは、実務において活用できる完成度の高いものだ。特に、カスハラの未然防止策に力を入れた内容となっており、消費者の権利を尊重しつつ、初期対応の重要性を強調している。
条例施行後の周知活動や支援活動が重要であり、特に中小企業に対する支援が欠かせない。行政だけでなく、業界団体の積極的な対策も必要だ。ACAPとしても、研修や例会、ホームページを通じて情報発信や個別支援を続けていきたい。
<プロフィール>
齊木茂人(さいき・しげと)氏
日本ハムの消費者対応部門責任者などを経て現職。カスタマーハラスメント対策の講演、研修を多数実施。2024年度厚生労働省ハラスメント防止対策企画委員、2024年度東京都「カスタマーハラスメント防止ガイドライン等検討会議」委員などを務める。